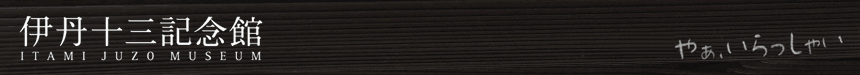受賞者
磯田 道史(いそだ みちふみ)
歴史家、国際日本文化研究センター准教授
 |
【プロフィール】 1970年12月24日、岡山市生まれ。 慶應義塾大学大学院卒。博士(史学)。茨城大学助教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、現在、国際日本文化研究センター准教授。 著書に『武士の家計簿』(新潮新書、新潮ドキュメント賞受賞、2010年映画化)、『近世大名家臣団の社会構造』(文春学藝ライブラリー)、『殿様の通信簿』(新潮文庫)、『江戸の備忘録』(文春文庫)、『龍馬史』(文春文庫)、『日本人の叡智』(新潮新書)、『歴史の愉しみ方』(中公新書)、『歴史の読み解き方』(朝日新書)、『天災から日本史を読みなおす』(中公新書)など多数。『無私の日本人』(文春文庫)の一編「穀田屋十三郎」が2016年「殿、利息でござる!」として映画化された。近著『日本史の内幕』(中公新書)、『素顔の西郷隆盛』(新潮新書) |
授賞理由
古文書を入り口に、本、新聞、テレビなどさまざまな媒体を通して、日本人の営みと歴史を問い直す情熱、知力、伝達力に。
伊丹十三賞選考委員会
受賞者コメント
この伊丹十三賞は、伊丹さんがそうであったように、多分野でマルチな活動をした人に授与されるときいた。それが、いただけたことは素直にうれしい。よい機会だから、この「伊丹さん的な生き方」が、この21世紀に大切になってくることを述べておきたい。
この国は、明治以後、西洋に追いつくため、狭い分野の「たこつぼ第一人者」という「ひとり者」を大勢こしらえて、急速な近代化をはかってきた。これが20世紀の日本の姿であった。このシステムでは、国家の期待にそって立派なひとり者になると「文化勲章」がもらえる。それが学者や芸術家の双六のあがりになっていた。
だが、この双六ごっこは、もう限界にきている。分野に垣根をいっぱいつくったものだから、いろいろ奇妙なことも起きて、21世紀になると、ひろい自由な発想が必要なものだから、狭い目の、ただの専門家ばかりを山ほど作った日本は、原子炉はわかるが津波はわからぬ経営者や技術者が原発事故を起こしてしまったり、技術開発や経済、学問芸術で明らかに遅れをとり、昔、植民地にした国や地域に、一人当たり所得で追いつかれたり、抜かれたりする状況になっている。
まあ、そんなことは、どうだっていいかもしれない。とにかく、わたしは好奇心がつよい生まれつきらしく、なりたいと思っても、一分野の専門家にはなれなかった。身の回りに面白いことがいっぱい見つかって、あれもこれも、やりたくなってしまう性分で、気がつけば、古文書解読や学術論文執筆だけでなく、これを一般向けの本にしたり、史伝文学を書いたり、映画化をはかったり、テレビで歴史番組を作ったり、ニュース解説までしていた。歴史にかんがみた地震津波防災の研究もやれば、狂言を書いて国立能楽堂で上演したり、戯曲を書いて上演したり、原作映画に役者として出演してみたり、忙しくて笑うに笑えない状態になっている。
ただ、今日の表現者は、伊丹さんのごとく、マルチ・多様なことがますます大事になってきている。伊丹さんのように、はっきり、自分の哲学をもって、この世の中をどのようにしたいか、どのような世界を望むか、その希望をこめた作品の発信が大切になってきている。
21世紀後半は、人工知能(AI)が発達するから、狭い専門分野のきまりきったことは、かなりの部分、機械がやってしまう。これからは、分野を横断的に生きる広い人間しかできない活動が重要になる。われわれは、そうすることで得られた知識や技能で、機械が思いもよらぬクリエイティブな発想を打ち出していかねば、ならぬ。そうでなければ、人間として生まれた甲斐がない。
人類史上、人工知能経済が生まれようとしている現代は、農耕開始や産業革命のような数百年か数千年に一度の変革期なのは間違いない。そんなとき、伊丹さん的な生き方、人間が人間らしく生きると、自然にマルチになるということを、いまいちど、考えたい。
磯田 道史