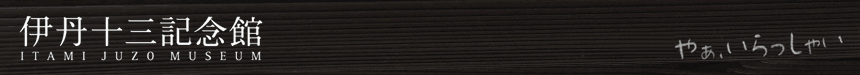第7回「伊丹十三賞」受賞記念
新井敏記氏 トークイベント(7)
2015年11月10日/伊丹十三記念館 カフェ・タンポポ
登壇者:新井敏記氏 (第7回伊丹十三賞受賞者/編集者、ノンフィクション作家、
スイッチ・パブリッシング代表)
松家仁之氏 (聞き手/小説家、編集者)
ご案内:宮本信子館長
松家 伊丹さんというのは、中学時代から繰り返し読んできたんです。僕にとっての「人生の先輩」、先生、ぼくのおじさん、なんですよ。テレビ番組やコマーシャルで姿を見ると、とにかく格好いい。果たして自分は、伊丹さんのように生きられるだろうか、みたいなことまで本気で考えましたから。全存在的に影響を受けました。
僕は新潮社に1982年に入ったんです。仕事にある程度慣れてきて、じゃあいよいよ自分が会いたい人に連絡をして会おうということになった。たぶん翌年の1983年だったと思うんですけど、伊丹さんに手紙を書いて「会ってください」とお願いして会いに行ったんです。それが最初でした。一番最初の時は、事務所のそばにあった、もう今はもう無い「狸穴そば」という、六本木の先の飯倉片町にある、すごくいいお蕎麦屋さんだったんですけど。そこに行って、初めて憧れの伊丹さんと向き合って喋ったわけです。
なぜかつづけて3回4回とお会いしたんですけど。4回目ぐらいの時に、「松家さんね。僕はこれから映画をやるんです。もうエッセイは書かない。そういう仕事はできないんだよね」ということを言われた。それが『お葬式』だったんですよ。最初の試写会に呼んでくださった……という。
新井 そうなんだ。
松家 だから僕にとっては、エッセイを依頼して、エッセイを書いてもらうということはついにできなかったんですけど、「これから映画に入るんだ」という瞬間、その伊丹さんと出会えたんだなという。
新井 ああ、すごい。
松家 そういう意味で言うと、特別なタイミングで伊丹さんに会っていたんだなって、いまになって思います。
新井 そうなんですね。
松家 その頃には手紙も頂戴しています。それはまだ記念館には手渡したくないので、今のところ自分の宝(場内笑)。でも、自分がだんだん危うくなったら――
新井 (笑)寄贈ですね。
松家 (笑)寄贈しようと思いますが、今のところは、絶対に渡したくない(場内笑)。
新井 (笑)
――僕の場合はね、大江健三郎なんですよ。
僕ね、15歳の時に大江健三郎になりたかったんですよ。

新井 日記に書いていたりするんです。
松家 「俺は大江健三郎になる」って?
新井 「大江健三郎になる」って。「作家になる」じゃなくて。
というのは、『芽むしり仔撃ち』という作品が大好きで。あの主人公に自分を投影できたんです。自分のまったく見たこともない山あい谷あいの村を、15歳で想像した。川に流されることとか、閉鎖された状況の中でどう生きていくかみたいなことをリアルに感じていたんです。
だから、僕が一番最初に大江さんにお目にかかったときは、本当に、松家さんにとっての伊丹さんかもしれないけど、そぞろ雨降る成城学園に、駅まで迎えに来てくださって、成城学園を案内していただいて。「これ、大岡昇平さんの好きな桜です」とか、歩きながら説明を受けて、至福の時を味わったんです。だから、松山に来るということは、僕にとっては、「大江さんに近い場所に来た」ということでもあったので。ドキドキしながらも、すごくあったので。
松家 『SWITCH』で大江さんの特集したのって、何年ぐらいでした?
新井 92年だったと思います。
松家 大江さんが表紙になっている『SWITCH』がありますね。このとき徹底して取材してましたね。故郷の大瀬まで行って。
新井 最初にインタビューをさせていただいたときは、「1時間だけ」という話でした。やっぱりそれが1時間で終わらなかったので、「じゃあまた来週いらっしゃい」といってまたやって、また終わらなかった。そりゃあそうですよね、こちらは、会いたくて会いたくてしょうがないし、いろんな質問があるし。だから、繰り返しやりとりさせていただいたんです。そのとき、「君は僕よりも風景に興味があるんじゃないですか?」と言われてドキっとした。『芽むしり仔撃ち』の舞台となった世界が見たかったので。「じゃあ大瀬に行きましょう」といってくださって、大江さんを案内人にいろんな場所を訪ねることができたのは、僕にとって、編集の30年の中で、たぶん最高の時だったんじゃないかなと思っています。
今回松山に来て、それをふたたび思い出して感じながら――と同時に伊丹さんの存在をあらためて思い描きながら――さっきも言いましたが、「宿題」というか「もう一回、特集したいな」と思ったんです。それは大江さんの特集であり、伊丹さんの特集です。自分にとって、どこか遠くに追いやってしまったことが、ふたたび頭をもたげてきたというか。それは、僕にとっては生き生きした瞬間をもう一回取り戻す大きな機会になるはずなんです。30年もやると、やっぱり飽きちゃうじゃないですか。倦(う)んじゃうというか。旅でも、「夢見た旅」と「余儀ない旅」のふたつがあるように。何度も同じ場所に行くと、自分はもう知っている場所だし、なんか飽きちゃったりするんですね。
自分にとって30年のあいだにいろんな軌跡があったんですが、もう一回この30年を機にこういう賞をいただいて、伊丹さんの決して手を抜かない仕事──口で言うのは簡単なことだけど、ものすごく難しいことじゃないですか──このことをあらためて考えました。僕は、ややもすると手を抜いちゃったり、ショートカットしちゃったりするんです。それはやっぱりダメなんじゃないかということに気づいた旅でもありましたね。
(松家さんに向かって)いつかまた、二人で伊丹さんの特集作りたいなって本当に思ったり、大江さんの特集作りたいなと思ったので。そしたら、またここに呼んでください(場内笑)。
松家 これがきっかけで、また松山に来ることになりそうですよね。
新井 ねぇ、呼んでいただけたらうれしい。松山ってやっぱり好きなんですけど、大江さんのこともあって、近くなったり遠くなっちゃったり。いろいろあるじゃないですか。恋愛感情と同じものがあるのかもしれない(笑)。
記念館でこうしてお話ができたこともすごく嬉しい。やっぱり何度も言うように、伊丹さんをもっと知りたいと思いました。僕は一回しか会えなくて、会えたことを何かかたちにすることまではできなかったけど、でもそれは、宿題が残ったということです。
僕はこの賞を、そのために頂いたんだなと思いました。ありがとうございました。
松家 ますますご活躍ください。
(場内拍手)
松家 どうもありがとうございました。宮本 ――今日は、新井さん・松家さん、本当にありがとうございました。まあ、なんと深い話をたくさん伺ったことでしょう。本当に幸せでした。
では頭を冷やしに、どうぞ桂の樹の方に皆さんいらしてください(場内笑)。
本日は誠にありがとうございました。
(場内拍手)

― 終演 ―